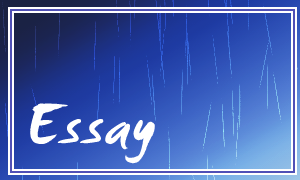創作行為で一番好きな表現方法は、と考えると最初に浮かぶのは書くことです。
普段の小説でしたり、こちらのようなエッセイや感想、場合によっては作詞や俳句にも挑戦したことはあります。まだ作品として結果を出せない未熟さがお恥ずかしい限りですが。
書くことは私にとって一番身近で大切な表現方法ですが、次に、一つの疑問が浮かびます。
なぜ、書くことなのか。
今回は私が書く理由について述べていきたいと思います。
あまりしゃちほこばらず、紅茶や緑茶、もしありましたらサブレやお煎餅とでも一緒にお読みください。行儀が悪いようでしたら、それらの食べ物は読後のお楽しみにしてください。
【特に小説について書くということ】
私の書くことについては、今回に限り「小説を書くこと」に絞らせていただきます。書くという表現だけでも、脚本に書道に短歌に論文と、様々な形態があります。それらを全てを網羅していると話が散らかってしまうので、今回は私が一番親しい「小説」を書くことを選んだ理由を軸にします。
私が小説を書くことを主な表現として選んだきっかけは、本が好きだからという、幼い頃からの経験によるものが発端です。それでも、脚本やシナリオではなく、小説の道を進むことにしたのは、設計図から作品の完成までを主に一人で作業することができるためです。そして、どうして一人で作業したいのかというと、私は小説を書くときにも、常に「問い」を立てるためです。
過去の作品を例に挙げますが、『花園の墓守』は「明日、世界が滅ぶとしたら」というキャッチコピーが作品を通しての問いにあたります。『無音の楽団 Re:Praying』はまだ執筆途中ですので伏せさせていただきますが、短編ですと『猫の尊厳』は「猫と人の共生のために地域猫などの活動をしているが、猫の自由として猫はそれらの活動を望むのか」になります。
そして、今回の主な例にさせていただく『砂糖だけでは食べられない』は「書く権利と読む義務」です。
短編であろうとも長編であろうとも、小説は完成までの作業に他者が介入することが他の表現活動に比べて少ない部類の表現であり、なおかつ俳句や短歌といった字数の縛りがないため、問いを立ててから答えを書くまで一貫することができます。
ただ、この先に進む前に気に留めてもらいたいことがあります。自身の考えの正しさを表現するために小説を書くのではなく、自身の問いを他の視点から見たらどう変わるのかも考えて、私は小説にしています。こちらについては後に頁を割きます。
まずはどうして、小説を書くときに問いを立てるのか、といった内容に移らせていただきます。
【問いからの答えは変化の一つ】
エンターテイメントの作品を制作する際には、ハウトゥ本でも「変化の必要性」が語られます。その例の一つとして、お手数ですが、こちらのリンク先のページをお読みください。
面白い作品には変化が起こります。「ドラえもん」であれば劇場版の「のび太の恐竜」でのび太君とピー助は二度別れます。一度はやむをえず。二度目は納得して。とはいえ、時には大きな変化がないままに、人気を博す作品もあります。ですが、大なり小なりどこか違ってくる点は生まれているでしょう。
私はその変化を書くことが正直なところ苦手な人間です。そのため、私は「問い」を冒頭か前半に立てておき、そしてその問いに対する「答え」をキャラクターが示す、といった作品が多いです。
「問い」は「課題」としても良いのですが、私の書く作品はいまのところ「答え」という形で物語に変化を出す作品が多いです。『砂糖だけでは食べられない』も「書く権利と読む義務が必要になった世界であるが、読者になるという義務を鎖火君一は放棄した」で締めています。こちらの作品で「央利に触発されて君一は読書を始める」でも物語になるのですが、私は「読む義務がある中でいかにうまく逃れるか」を書きました。
どうして「変化」を「問いと答え」という形にして小説を書くのかというと、私はささやかながら、哲学を志す者です。ただ書くだけではなく、いまこの時も顕在している問題について考え、それらを小説にしたいのです。
どうして小論文やレポートといった形ではなく、小説にしたのかについてですが、「変化」という手段と「哲学」が私の中では上手く噛み合ったためです。
哲学は常に森羅万象に疑問を抱き、解式のある答えを出すことが重要です。そのために生まれ、退けられ、見直され、といったことが繰り返されてきました。
私はそうした哲学の営みが好きです。同時に、小説の読む快楽にも耽溺しています。この辺りは言葉にすることが難しいのですが、「教養」でもなく「娯楽」だけでもない小説を私は書きたくて、作中の変化という機能に「問いと答え」を当てはめたのです。
【一つではない答えをまずは一にする】
「問い」の「答え」を出して小説を終わらせます。ですが、その「答え」は私の考えと繋がっているとは限りません。私の思考から生まれたものですから、私の要素が入ることは避けられませんが、物語の登場人物として、どう答えを出すかは常に意識して書いています。
『砂糖だけでは食べられない』では央利に「試読権」を代替わりさせていても、さほど罪悪感を抱いていない君一と、君一から「試読権」を受け取って代筆する代わりに、読むことのできる作品を増やしている央利がいます。
こちらは、どちらが正しいわけでもないのです。君一は読むことに興味を抱かないために、央利に権利を渡して、代筆という楽をしています。央利は先ほども書いた通り読書の機会を増やすなど、お互いに納得して得をしています。
それだけの話です。
解釈は書いた私自身、こちらの作品に対していくつかはできます。君一を批判することも、央利は何に対して哀れんでいたのかを考えるなど。
ですが、作中で一旦、答えを出した私はもう他に語ることはありません。こちらの作品の「問い」に読者の方が気づいて、それぞれの答えをさらに発展させてもらえたら、嬉しいです。
一つとは限らない答えを、まず作者が明確に一と定義する。それによって、読者は様々な答えを膨らませることができるようにします。
前の項では「変化」として「問い」を立てると書きましたが、考えを膨らませることを可能にする「問い」は哲学の意図として立てます。
上記をまとめると、私にとって小説を書くこととは「問いを立てて、考え、答えを出す」という一連の行為を作品として昇華するためです。
そして立てた「問い」をどなたかが受け取って、さらに答えを見つけてくださると、幸いです。
(初出 2026年1月10日)